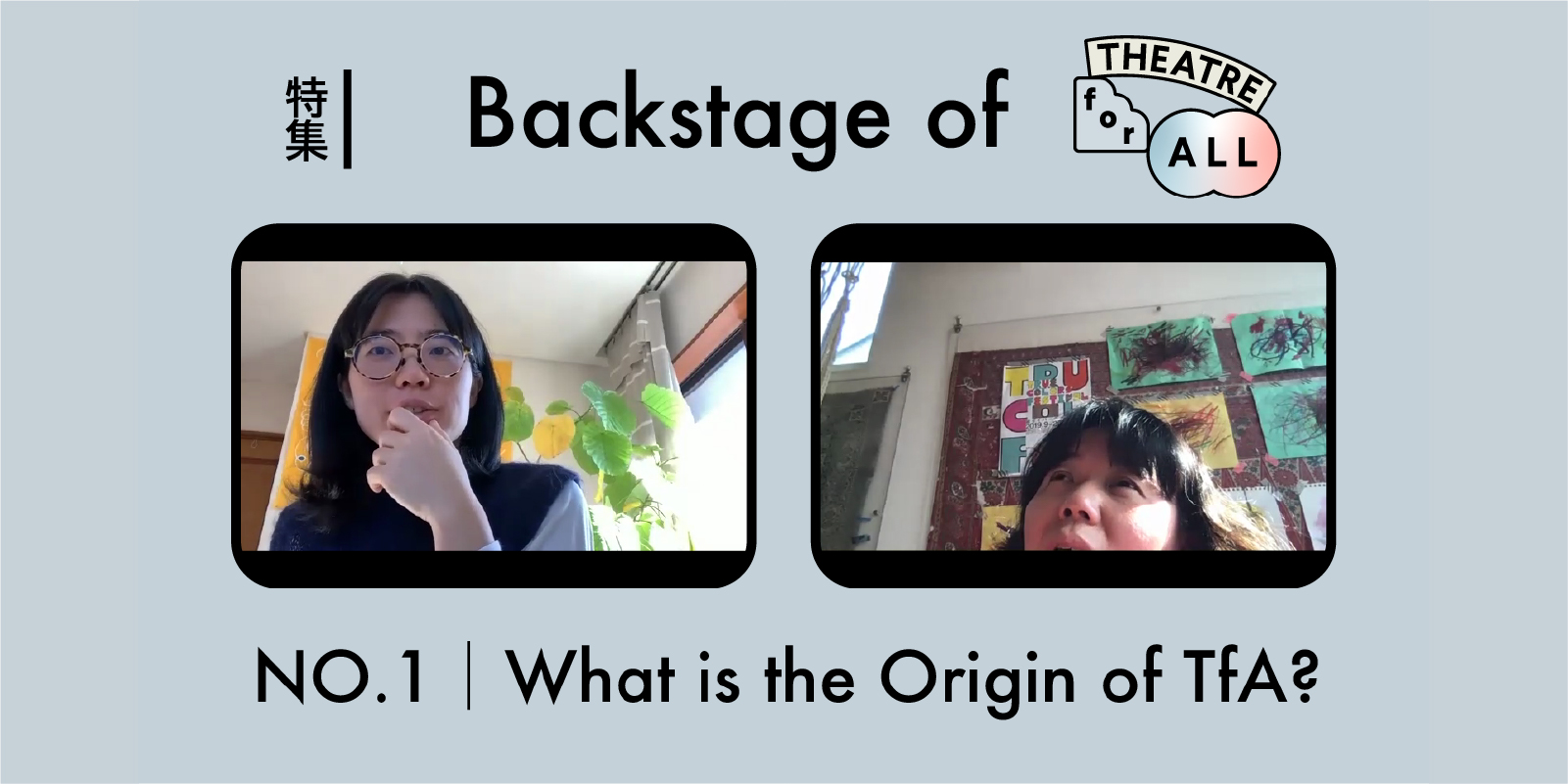投稿日:2021/04/13
N0.1|What is the Origin of TfA?
パフォーミングアーツの制作会社、プリコグの代表である中村茜と、ファッションとコミュニケーションデザインといった領域で活動してきた金森香。これまでも数々のプロジェクトでタッグを組んできた2人がプロデューサー(中村)とディレクター(金森)という形で手がける「THEATRE for ALL」。2人の言葉から、アクセシビリティ×オンライン演劇にたどり着いた背景と、その挑戦の意図に迫る。
—まずTHEATRE for ALLを始めようと思った経緯を教えてください。
中村茜(以下、N):私は、もっと芸術を社会に開かれたものにしたいという思いをもっています。例えば、劇場というと日本では、多くの人にとってちょっと非日常的な「特別な場所」という距離感だと思うのですが、パリやベルリンで劇場文化に触れると、もっと日常のそばにあります。母娘で観劇前に劇場のカフェで食事して、観劇して、家族の対話が弾んでいる風景などもよく見てきました。劇場に付属のカフェが安くて美味しいところが多いので、公演じゃなくても、劇場が地域コミュニティ拠点として機能しているような根づき方です。そんなふうに、図書館に子どもが通ったり、公民館でおばあちゃんたちがお茶したりするような社会教育機関としての日常性を劇場が持っていて欲しい、という思いもあります。
そして、2000年代ごろから抱いていた構想の一つとしてあるのが、イギリス・ウェールズが拠点の「National Theatre Wales」のようなオンライン・アートセンターをつくりたいというイメージです。ナショナルシアターと言うと、ある種権威的で、大きな建物があり、そこに芸術家や鑑賞者が集まって……というイメージになりがちなのですが、そこでは劇場という特定の活動拠点をもたず、様々な地域で公演やワークショップ、イベントを行なっていました。オンラインであれば、よりフレキシブルでフラットなあり方で場所に縛られることなく展開できます。
また、コロナ禍でオンラインの可能性をより感じたことで、構想に拍車がかかりました。個人的にも演劇や映画を配信で観る機会が増えましたし、ソファに座って家族と一緒に作品を観ていると、クリエーションや鑑賞という行為が日常のなかに入り込みだしたタイミングだと感じました。
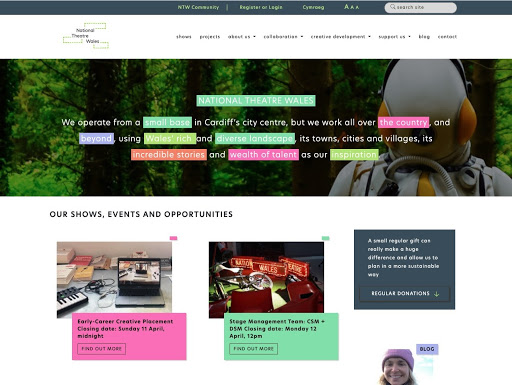
—THEATRE for ALLはバリアフリー型というのが特徴のひとつだと思います。バリアフリーに対する試みは、どのようにスタートしていったのでしょうか?
N:障害・性・国籍・言語・世代などの、“違い”をテーマにした芸術祭「True Colors Festival」(以下TCF)で、劇場やイベント会場の鑑賞サポートの取り組みを行ったのが、大きなきっかけでした。一言で障害と言っても、身体障害や知的障害など事情は様々。差別や偏見の歴史や、社会的な課題も含め、一筋縄ではいかない複雑な社会状況にたいして、きちんと向き合えるのかという不安はもちろんありました。仕事としての挑戦の舞台が用意されていなかったら、飛び込んでいけなかった領域だと思っています。
ただTCFを通じて、今後挑戦したいことが色々生まれていたことも事実です。結局新型コロナウィルス感染拡大で、TCFは中断してしまいました、その無念の思いをぶつける場所として、文化庁で文化芸術収益力強化事業の募集を見つけたんです。前々からオンラインが持つアクセシビリティの可能性については金森たちとブレストもしていて事業の準備も始めていたので、向かう方向性は最初から見えていた。だから、構想から立ち上げまではすぐでした。
※TCF:True Colors Festival(トゥルーカラーズ フェスティバル)。パフォーミングアーツを通じて、障害・性・世代・言語・国籍など、個性豊かな人たちと一緒に楽しむ芸術祭。“超ダイバーシティ芸術祭”と銘打つ。
金森(以下、K):私はファッションの業界に長くいながら、想定する利用者像があまりに限定的であることに違和感を感じ続けていました。製造方法や収益構造のモデルが量産前提としていることが大きいともいえますが、目指すべきビジョンの示し方としても、世界のある部分にしか向き合っていないような、バランスを欠いた状態だと思っていました。そんな問題意識もあり、多様な身体や、障害のある方々とのファッションショーを過去にも企画したことがありました。日本科学未来館で田中みゆきさんの企画する「義足のファッションショー」に携わらせていただいたのをきっかけに、2017年に「オールライトファッションショー」を岡山で開催し、高齢者や脳性麻痺の方、車椅子、杖などを使う人たちに合わせてプロのファッションデザイナーが1点物の洋服をつくり、ショーをしました。
このような企画を実行するなかで感じたのが、つくるまでのプロセスのなかで発生する対話の中にこそ学びがある、ということです。わたし自身もそんな過程を経験したからこそ、今回TFAでは、成果物はもちろん重要だけれど、そのプロセスにも視聴者の方々が健常・障害をとわず関われるような仕組みとは何か、そこでの気づきをどのように可視化し、共有できるのかを考えています。そんな思いもあり、TFAのラボ事業、コミュニティ運営、ラーニング事業がうまれました。

—「障害」だけではない「インクルーシブ」という視点で言うと、どのようなことを行なっているのでしょうか?
N:私たちのプログラムは2/3が公募なのですが、そこにインクルーシブな視点で新作をつくれる枠を設けました。この枠で求めているのは、既存の作品に後から字幕や音声ガイドなどの情報保障を施すやり方とは異なるアプローチの試みです。創作メンバーに様々な体や知覚をもつ方がいて、企画段階から色んな視点を交えて構想された作品が出てくるといいなと。
TfAはインクルーシブな視点をきっかけにした時にどういう表現が生まれるのかを試す場所でありたいと思っています。私たちは「ダイバーシティであることが、美しい」といいたいわけではないんです。それぞれの当事者性から、どんな表現が導き出せるのかに関心があります。障害だけでなく、外国語話者や、子供といった様々な当事者性を発揮できるアートのフォーマットが必要だと思っています。
K:ちょうどこのまえ「当たり前だと思っていた前提や知覚を疑うことによって、他者に対する想像力をたくましくしていく試みがバリアフリーなんだね」とあるアーティストに言われたことがあります。いわゆる音声ガイドや字幕なども重要ですし、提供し続けて行きたいと考えていますが、いっぽうで、インクルーシブな思考が創作段階から入ることで、表現そのものが変わってくるだろうなと実感しています。
—TfAの事業はアクセシビリティ、学び、アーティストのクリエーションによって構成されています。このなかで「学び」に該当するラボやラーニングはどのような構想のなかで生まれたのでしょうか?
K:作品の制作プロセスや、鑑賞体験における気づきを共有することはもちろん、日常的に福祉施設の人と話したり、研究者とコミュニケーションをしていくなかで得られる気づきを貯めていきたいと考えて構想しました。一直線にアウトプットのための方法を探るだけではなく、もっと寄り道をして色んな方向から情報収集できるような場所を持っておきたいかった。そんな思いが、ラボの背景にあります。
N:ラーニングに関しては、作品の前後にワークショップを入れることで作品自体を教科書にする『コネリング・スタディ』という実験を2019年ごろから行なってきたこととつながっています。例えばパフォーマンスをイラスト化するワークショップを事前にやってから、実際に演劇を観ながら絵を描いて、皆で感想をシェアするような取り組みです。ひとりひとりの脳が世界を全然違うかたちで捉えていることがわかって面白かったんです。
こういうことを見える人/見えない人、聴こえる人/聴こえない人といった多様性のなかで行なえれば、さらに多くの学びに繋がると思いました。そもそも人はみな当事者です。それぞれの視点を交わせる機会が増えていくのは大事なこと。ラーニングでは、色々な見え方を共有していきたいんです。芸術が社会に開かれ続けるために、そのあり方を再構築する場所にしていけたらいいなと。
—TfAにはシアターという空間を意味することばが入っています。すべての取り組みは「場」というキーワードで繋がってくるように思います。
K:様々な人たちが対話する場をつくることは我々の生活する社会そのものを豊かにするために必要なことです。わたしたちのつくる「THEATRE」が、そのような場になることを目指したい。TfAは芸術鑑賞のためだけではなく、作品の鑑賞をとおしてそれぞれが何か気づきを得たり、異なるそれぞれの当事者との対話をするきっかけを生み出し、意見をシェアし、そして対話の方法を学んで実生活でも実践してまたここに帰ってきて話し合える、そんな開かれた場所にしていきたいと思っています。