投稿日:2021/02/26
コンテンポラリーダンスを今よりも多くの人に楽しんでもらうためには、どうしたらいいのか? 映画には字幕や音声ガイドがあるが、その役割にあたるものはコンテンポラリーダンスにはない。とくに今回は、視覚障害者にダンスを観賞してもらう方法を模索している。
#ダンス #アクセシビリティ #視覚障害 #研究会 #DaBY
©Naoshi HATORI
“見える”が異なる。5名の視覚障害者によるダンス観賞
2020年12月27、28日。「ダンスのアクセシビリティを考えるラボ」と題する研究会では、この2日にわたり合計4名の「言葉のプロ」がディスクライバー(「描写する人」の意)となり、視覚障害者のダンス観賞を実践する。まず、なんの解説もなく5分ほどのコンテンポラリーダンス作品を観賞。その後、4人のディスクライバーがディスクライブしながらダンス作品を上演するというワークショップをおこなう。
27日に参加した視覚障害者モニターは5名。それぞれにとって「見えない」ということが異なる。学生の藤本昌宏さんは、生まれた時から全盲で色も光も経験したことがない。伊奈喜子(よしこ)さんは小さな頃に全盲となり、色のイメージは記憶がある。25歳くらいで全盲になった山崎康興(やすのり)さんは、見えていた頃の感覚を覚えている。そして、井戸本将義さんは全盲ではなく、右目は見えないが左目のみ視力0.02で視野が「ラップの芯の棒を覗いたくらいの狭さ」だそうだ。中川美枝子さんも10歳くらいから全盲で、『視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ』代表の林建太さんと共にこの日のファシリテーターを務めた。
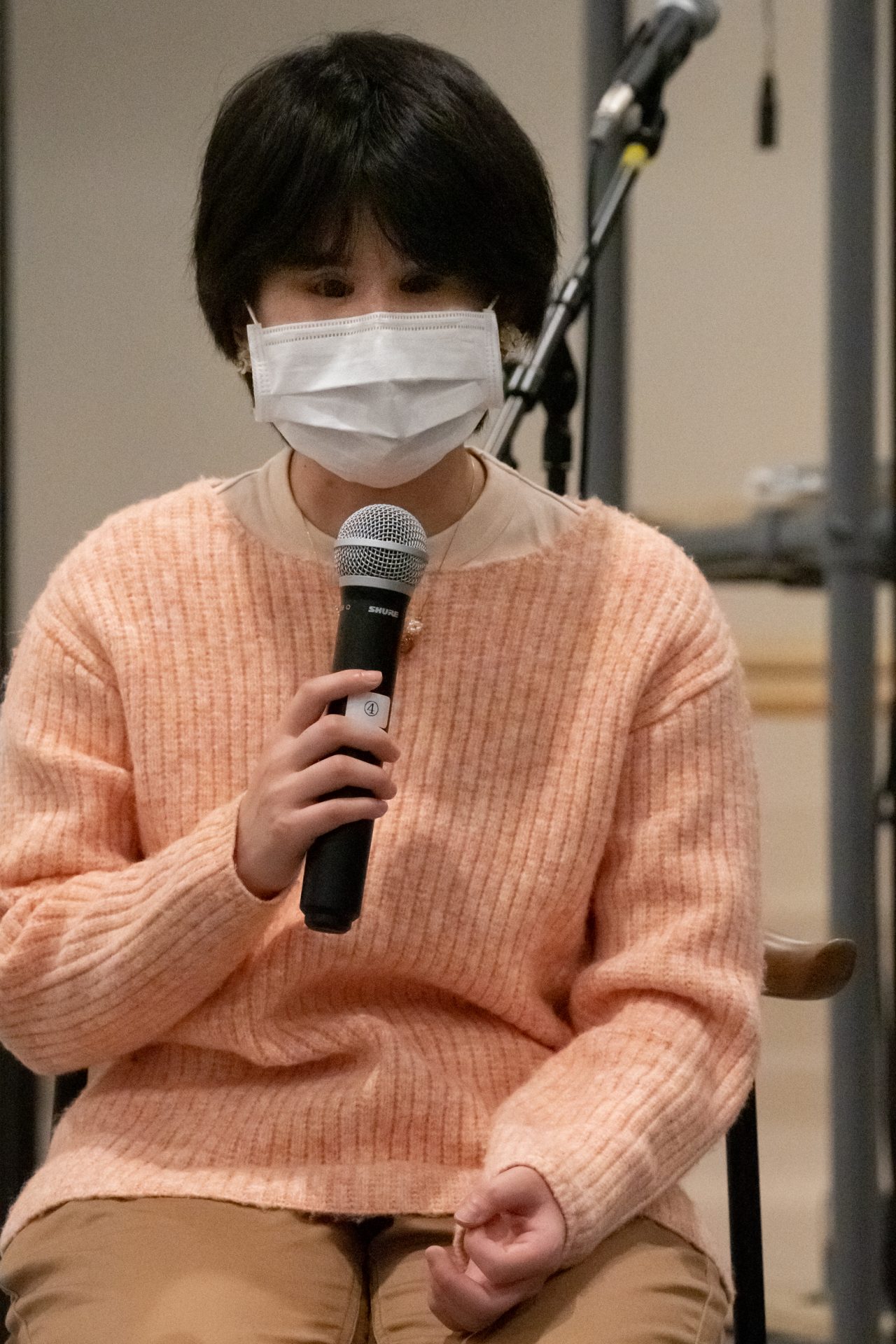
モニターのみなさんは、初めてのダンス観賞を前に「未知の領域で楽しみ」「好きなアニメ観賞の経験が、ダンス観賞にもいかせるのか知りたい」「ひとつのダンスが伝えてくれる人によって印象が変わるだろうから想像できない」など、期待が高まっているようだ。
●タッチツアーの実施
ダンス観賞の前に、空間を把握する『タッチツアー』をおこなう。スタッフがモニター5名の手を引いて、スタジオを案内する。「4本の柱があります。大きさは抱きついてみてください」「床はグレーのリノリウムです」など説明し、場所の全体像を理解してもらう。モニターの方々からは「柱が丸いのに意味はありますか?」「このスペースのどこで踊りますか?」「光はどの方向からさしますか?」などの質問があがった。質問には丁寧に回答しつつも、基本的には、まっさらな状態でダンス観賞をしてもらうため、スタジオ空間最小限の説明にとどめる。
最後に、小道具(金属の棒の山)にも触れて感触をたしかめてから、ダンス観賞がはじまった。
●ディスクライブ無しのダンス観賞

まずは、なんの説明(ディスクライブ)もなく作品を上演する。チェロの生演奏と、4人のダンサーによるダンス。時々、小道具である金属音も聞こえる。
上演後の感想は「無言劇というかんじ。そもそもストーリーがあるのかな?」「生演奏に聞き入ってしまった。ダンサーさんはなにをしていたんだろう」「もぞもぞ動いてる音とか、ところどころでカサっと人の動きがそろったような音がした」と、なにがおこなわれていたのかはわからない様子だ。この“なにがおこなわれているかわからない”体験をベースに、4つのディスクライブが入った観賞体験と比べていく。
4人の「言葉で伝える」プロによる、4パターンのダンス観賞ガイド
●ディスクライブ①:伊藤亜紗さん
伊藤亜紗さんのディスクライブは「触覚」と「言葉」でおこなう。伊藤さんは書籍『目の見えない人は世界をどう見ているのか』『目の見えないアスリートの身体論――なぜ視覚なしでプレイできるのか』などを執筆してきた研究者だ。ディスクライブでは、触覚の研究者であり、『見えないスポーツ図鑑』の共著者でもある渡邊淳司さんが、助っ人として参加した。
伊藤さんが取り出したものは、4本の手ぬぐい。モニターの4人に手ぬぐいの端と端を握らせ、輪になってもらう。4人を繋ぐ、4本の手ぬぐい。その中央を4人の晴眼者がそれぞれ持ち、ダンスに合わせて手ぬぐいを上下したり引っ張ったりして動かすのだ。

ダンスがはじまると、晴眼者が手ぬぐいを動かすのと同時に、伊藤さんがダンスの状況を言葉で説明する。「まんなかにチェロがいて、みんな黒い服を着ています」「いまダンサーがひとり入ってきました。金属の上に乗っています」。
伊藤さんの説明を聞いてはじめて、モニターの伊奈さんは「ダンサーは男性がひとりで、ほかは女性なんですね」と気づいたようだ。また「手ぬぐいの動きがゆっくりだったり早くなることで、スピード感と雰囲気が伝わってきた!」と体感を楽しむ一方で、「ダンサー同士の距離感がわからない」「手ぬぐいの動きが、個別のダンサーあらわしているのか、ダンス全体をあらわしているのかわからない」という混乱もあった。そもそも、コンテンポラリーダンスというものがどんなものかわからないため、かなりイメージすることが難しいようだ。
モニターの方だけでなく、ダンサーの動きを手ぬぐいで伝える晴眼者からも、「手ぬぐいを使ってどう伝えればいいのかわからない」と難しさが語られる。一方で、「手ぬぐいを動かしたらモニターの方がついてきてくれ、一緒に踊っているみたいだった」と共鳴を楽しんだ瞬間もあった。
感想をうけ、ではどうしたらダンスが伝わるのか、いくつかのアイデアが出される。「どうすれば伝わるか?」「どう伝わると楽しめるか?」と活発なディスカッションが交わされた。そのなかで「手ぬぐいよりも手のひらの方がダンスをストレートに伝えられるのでは?」というモニターの山崎さんの発案により、ステージに近い四角い形をしている背中をキャンバスに見立てて、手のひらや指でダンスを伝えるディスクライブをおこなってみることに。ダンスに合わせて、背中を指でツンツンと押してみたり、手のひらでぐるぐると大きく撫でてみたり。「面白い!」「ダイナミック!」と手ぬぐいよりも興奮する声が聞こえてくる。

ただ、ダンスの雰囲気は伝わるものの、やはり手の動きがなにをあらわしているのかわからない。また人によって、手の動きで表現することが得意な人・苦手な人がいて、誰が伝えるかでかなりダンス観賞体験に差が出てくる。たとえばダンサーなどが行う場合は「手による表現が豊かでわかりやすい」と、目の前のダンスの情報がより正確に伝わる。一方で、手の動きがぎこちない場合には「初めて観た戸惑いも伝わってきて、ダンスを体験している感じがでる」「人によって伝えたいことや伝え方が違うので、同じダンスでも何度でも楽しめる」など、ダンス観賞を体験することができるとの意見もあった。
それからも、次々とアイデアを出しあっていく。バリエーションを出してみるために、道具も使ってみる。ぼこぼこのついた手袋や、つるつるのビニール袋……試してみると、道具によって、背中に伝わる感触が違う。アイデア出しにはモニターの視覚障害者たちだけでなく、作品の振付をした鈴木竜さんやオブザーバーとして参加したDaBYレジデンスコレオグラファーでダンサー・美術家のハラサオリさんも加わり、「もっと体重をかけたら?」「作品の小道具の金属棒を使ってみたら?」など新たなディスクライブの方法が生まれていった。

振付を担当した鈴木さんは「ダンスへの解像度が、翻訳者によって違いがあるのが面白い。あまりシステマティックになっても、ダンスの体験が失われるんじゃないかな」と、自身のダンスが他人を通してどう伝わるかに新鮮な驚きを感じているようす。モニターの藤本さんも「翻訳者が変われば伝わる情報が変わる。人によって伝えたいことが違う。同じダンスでも何度でも楽しめる」と前向きだ。
言葉だけでなく、触覚を使って伝わってきた情報をうけて「実際には踊っていなくても、ダンスを体験することができたかもしれない」と、身体性を強く感じたダイナミックなディスクライブだった。
●ディスクライブ②:大崎清夏さん
詩人の大崎清夏さんは「ディスクライブというより、翻訳をしました。わたしは詩は世界の翻訳だと思っていますが、今回も“身体の詩(=ダンス)”を“言葉の詩”に翻訳する行為だったと思います」という。2週間ほど前から作品の映像を何度も観て、振付家の鈴木さんとダンサー4名にいくつか質問に答えてもらった。そのうえで、ダンスを言葉にした。本人たちの視点を意識した言葉は、ダンサーの内面を描写するように紡がれていく。

上演中、事前に書かれた詩を大崎さん自身が朗読していく。一人のダンサーが登場し、金属の棒を地面に垂直に立てようとすると、「鉄の枝が垂直に立ち始める。あなたの理想の垂直だ」と大崎さんの声がチェロに重なるように響く。残り3名のダンサーも加わると、「あなたが4人いるようにみえる。あなたの挑戦が4倍になる」と大崎さん。そこからはさらに3名の朗読者が加わる。4人のダンサーが同じ動きをする時には、4人の朗読者は同じ言葉を発する。「「「「光。斜めに、重心が偏っていく」」」」。しかしダンサーたちがバラバラな動きをする時には、朗読者の言葉もバラバラになる。ダンサー1人につき1人の朗読者がその動きを語るのだ。まるで4人の身体によるダンスが、目を閉じれば4人の言葉によるダンスになったようだ。
ふだんダンスを観る晴眼者にとっては「実際にダンスの群舞を観たときの感覚に近い」という反応が強くあった。しかしモニターの方々の反応は、言葉が重なり聞き取りづらかったことに不安もあった。「ダンサーさんごとにわけて朗読してくれたけど、ステレオゲームみたいな感じ。音楽との音量のバランスも一人ずつの方が聞き分けられる状態だったらよかった」「(小道具の)金属のガシャンという音や、チェロの音色に言葉がかき消されてしまった」と、言葉の意味を知りたがる声が多かった。
しかし、言葉が重なるのは意図的だ。「自分がダンスを観る時、ステージの一か所を見ている間にほかの場所を見逃すということが無限に起こる。そういうことも感じてもらえたらと考えた」。
大崎さん独特の言葉の表現は、モニターの方々の興味を引いた。ダンサーを“あなた”と呼んだり、その“あなた”の内面を語る詩的な表現が多い。たとえば、金属の棒を床に立てようとするが棒は倒れる……というシーンでは「倒れる」ではなく「失敗する」と言い、ダンサーの動きが主観的に語られる。実際に踊ったダンサーからは「言葉と一緒に作品を作り上げているような感覚。踊りと詩の作品という一体感がうまれたんじゃないかな」「良いことかはわからないけど、踊っていて気持ちが乗りやすかった」など、ダンスと言葉のコラボレーション作品のような印象が強かったようだ。モニターの方もまた「音楽と言葉が一緒になって、言葉が音楽の一部みたいに聞こえてきた」と、大崎さんのディスクライブをダンスの解説ではなく、作品の一部として楽しんでいた。言葉が入ることで、新たな作品がうまれたようでもあった。


2つのディスクライブが行われた時点で、「見る」ということについて、視覚障害者と晴眼者にある違いがあることがわかった。数名のダンサーは、①の伊藤さんのディスクライブではモニターは手ぬぐいや背中に意識を集中していたからか、存在を遠く感じたと言う。しかし②の大崎さんのディスクライブでは寂しさがなかったそうだ。一方で、モニターからは真逆の意見が出た。うつむいて耳を傾けた方がより集中して相手の話を聞くことができるが、目が見えている人と話すときは相手が違和感を感じないように顔の方を向くということだ。目の見えている人は相手と顔を合わせることでコミュニケーションしている実感があるが、視覚障害者は相手に集中しているがゆえに相手の方を向いていない場合もあるという。
ライブパフォーマンスのひとつは、ステージと客席の双方向に関係が生まれることにある。しかし、相手の方を「見る」ことが関係するということでないのなら、コミュニケーションとはいったいなんだろうか。
その後も「コンテンポラリーダンスはよくわからないと言われることが多いが……」という前提のもと「わからないことを、言葉で伝えるとはどういうことか」と議論がつきない1日目だった
●ディスクライブ③:乗越たかおさん
研究会最終日の28日。モニターは前日の藤本さんと井戸本さんに加え、ダンス好きの娘がいるという全盲の松本晶子さん(生まれた時は弱視)が参加し、5歳で全盲になった浦野盛光さんが林さんと共にファシリテーターを務めた。
3つ目のディスクライブをおこなう舞踊評論家の乗越たかおさんは、ダンスを言葉で伝えるプロフェッショナルだ。さまざまな評論家のなかでも乗越さんについて、DaBYアーティスティックディレクターで、今回は研究会全体のコーディネーターとして参加した唐津絵理さんは「ダンサーたちの世界に寄り添いつつ、お客様がどう見えるか、繋ごうとしている。評論というよりコミュニケーションをとろうとする姿勢が、ディスクライブに向いてるんじゃないかと思っていました」と話す。
乗越さんのディスクライブは、目の見える人が得ている情報にできるだけ近いものを、視覚障害者のモニターに伝えることに努めたものだ。それを、コンテンポラリーダンスの実際の現場にもっとも近い言葉を用いておこなう。
まず、ダンス観賞の前に、コンテンポラリーダンスという未体験のものについて、5分ほどのワークショップを実施した。「ダンスにはストーリーがあるものや、ステップを覚えるものだと思われるかもしれませんが、コンテンポラリーダンスはもう少し幅が広い。身体を動かすこと自体が楽しいんだということを共有したうえで、ディスクライブに入れれば」。さらに乗越さんは「椅子ではなく床に直接座った方が振動を感じられるのでは」と提案する。前日の研究会で、視覚障害者のモニターから「うつむいて耳を傾けた方がより集中して相手の話を聞くことができるが、目が見えている人と話すときは相手が違和感を感じないように顔の方を向くように意識している」という話を聞いたことに、すくなからず衝撃をうけたからだ。乗越さんの提案により、モニターらは床に直接座り、チェロの生演奏のなかで、乗越さんの声に誘われるように、腕を上げたり、下げたり、ぶらぶらさせたり。ふだんの生活では意識しない腕の重みや動きをゆっくりと実感する。「右手の人差し指を中指を左手で掴んで、息を深く吸いながら、両腕をぎゅーっとあげて、下げる……。腕って実は重いということを感じてみてください」「身体はからっぽのイメージをしてください。中には風が吹いてます……溶岩になって……寝っ転がって……おやすみなさい」。身体の中をイメージが通り抜け、スタジオの体温がすこし上がったような空気に包まれた。乗越さんは観賞前に、ダンサーの動きやチェロの音をより感じるために「なんなら床に寝転がってもいいですよ」と付け加えたところ、全員が床に寝そべった。


乗越さんにより前説があり、作品・鉄(小道具)・衣装など上演チラシや当日配布パンフレットに掲載されているような基本的な情報が説明される。その情報を得たうえで、乗越さんの言葉によるディスクライブつきの作品上演がおこなわれた。ここでもモニターたちは、寝転んだり、耳を床に押し当てたりと、思い思いの恰好で観賞する。「黒い塊の上に乗る。ぶつかり合う金属。どうやら、錆びた鉄の棒やパイプのようだ」「一本の棒を手にとる」「棒の長さは肘から指先まで」。乗越さんの説明は、描写が細かく、客観的で、具体的だ。
観賞後、モニターからは具体的な理解が進んだ驚きの声が多くあった。「圧倒的に情報量が多いところが良かった。何回も観賞しているにも関わらず、わかっていなかったことが多かったとわかった」「見えているのと同じ順番で情報が入ってくるみたいだった。たとえば「あの黒い塊はなんだろう?……あ、金属か」のように、見えている人の心の動きがわかるようだった」「ただ解説するのでなく、ダンサーの動きを『進む。進む』というように繰り返すことで盛り上がりも感じられた」「実況みたい。僕のイメージするディスクリプションに近い」。
また、今回初めてダンサーの動きの具体的な描写がでてきたことで、より「ダンス」というものの正確な形がイメージできてきたようだ。「これまでは自分でも踊れるものが上演されているのかなと思っていたけれど、ダンサーさんがプロフェッショナルな難しいことをやっていると理解できた」「動作を中心とした言葉が多かったので、こちらも主体的に、一緒に踊っているような感じを持てた」。ダンサーからも「乗越さんの言葉は舞踊的。現場に近い」と共感の声があった。
なぜこの言葉を使ったのか?と質疑応答があるなかで、乗越さんの言葉は具体的な描写だけでなく、自身の視点も入っていることがわかってくる。「たとえば『明かりが暗く、人が入ってきた』とそのまま説明しても面白くないので、『寂しそうに見える』などイメージを喚起する言葉を少し盛り込んでいった」。そう振り返りを重ねるうちに、視覚障害者とコンテンポラリーダンスの相互理解が深まっていく。長年ダンスに携わってきた乗越さんからは「寝そべって観賞することは劇場ではできないけれど、目の見えない人がダンスを観る方法としてありうるのだと感じた。目が見えないことについていろいろ考え抜いてディスクライブをおこなったつもりだったが、わかっていないことがまだまだある。あらためてそのことに気づくことができた」と、この研究会を貴重な実感として受け止められていた。

●ディスクライブ④:和田夏実さん
最後は、和田夏実さんによるディスクライブ。ふだん手話通訳などもおこなう和田さんにとって、ディスクライブとは、視覚的なものを伝えることではなく、“内面”を伝えることではないかと考えたと言う。そのためにも、視覚障害者が作品に飛び込むように観賞できる方法がないかと模索し、ダンサーやモニターに時間のゆるすかぎり質問を投げかけてきた。
インタープリター(通訳者、解説者)の肩書で活動をする和田さんは「インタープリターは、間に立つために“解釈”をします」と説明する。「企画の意図を細かくヒアリングし、どう受け取りたいか、なにが目的か、なにが優先されるかを判断していきます。また解釈者として、ヒアリングによって作品の意図や、ダンサーの感覚を探します」。

ディスクライブにあたって、和田さんは色々な物を持ってきた。ガーゼ、ボウル、枯れた花のオブジェ、瓶、瓶、ドライフラワー、タオル、リンゴのオブジェ、針金できたリンゴ、岩、髪ゴム……。それらをモニターに手渡し、感触を確かめていく。また、事前にモニターの方々に持参をお願いしていた「時間のあるもの」も、順番に触ってもらう。たとえば、ぬいぐるみ、ガラケー。そのほか、さまざまな物に触れたあと、ダンスの本編が始まった。
上演に合わせて言葉でディスクライブするが、和田さんの言葉は抽象度が高い。たとえば、ダンサーが鉄の棒を床に立てていくシーン。大崎さんが「鉄の枝を垂直に立てる」、乗越さんが「棒を床に立てる」と言葉にした部分を、和田さんは「地球のうえに立てる」「わたしのなかに立てる」言い、鉄の棒のことを「過去」と表現した。この「過去」は、作品創作のなかで振付家の鈴木さん自身から出た言葉だ。和田さんの選ぶ言葉は、振付家やダンサーの、創作意図や内面に寄り添って立ち上がっていく。それは、誰かのバックグラウンドも踏まえたうえで他者に伝えるインタープリターの役割のようである。
上演後の感想は、「謎が増えた?」「4つのなかでもっとも衝撃的」という驚きとともに「だからこそ楽しかった」というものが多かった。「なにがはじまるんだろう、わかんないわかんないわかんない、と思いながらどんどん本編に入っていく感じが面白かった。途中で、これはこういうことかもしれない!と気づいたり、新たな価値観が見えて世界が広がった」。こういった声をうけて、ダンサーたちからも「晴眼者がコンテンポラリーダンスを観たあとに出てくる感想に近い」と驚きの声があがった。
4つのディスクライブを振り返って ~ディスカッション~
4パターンのダンス観賞を終えて、振付家の鈴木さんはそれぞれの違いをこう分析する。「伊藤さんは見る人に寄り添って、大崎さんは踊る側にふりきった。乗越さんは、外から客観的に説明する。和田さんは、ヒアリングのなかで僕が答えた言葉が入っていてしっくりきた。作品を作った立場からすると、たとえば大崎さんのディスクライブが寄り添ってくれる感じがしてぐっとくるし、乗越さんのは『そう見えるのか』と発見が多い」。
その場にいる研究会メンバーの誰もが、現時点でのコンテンポラリーダンスにおけるディスクライブの正解のなさを実感しているようだ。それは、モニターの藤本さんの言葉にも繋がっているようだ。「このダンスの作品は誰のものなんだろう? 4つともまったく違って、4つとも作品に入り込むことができた。そうなると、ダンスについてディスクライブするための言葉ってなんだろう」。モニターの井戸本さんからも「どのくらいコンテンポラリーダンスに詳しい人が観賞するかによってどういった方法で楽しめるのか違うのかも」と、コンテンポラリーダンスにおけるディスクリプションについて問いが投げかけられた。
●「ダンスとはなにか?」をあらためて問う
研究会は、これまでダンスを観てきた晴眼者にとっても、あらためて「ダンスとはなにか?」と向き合う時間となった。研究会を主催し、実施会場ともなったDaBYのミッションは『ダンスを社会に拓いていく』だが、この研究会でバリアフリーと向き合う社会にダンスを拓いた結果、「ダンスは誰のものなのか?」「見えていると思っていたものはなんだったのか?」と、ダンスにあらためて真正面から向き合ったという声も聞かれた。
3日間を通して「いろんな人の視点が聞けて、自分の世界観が広がった」という発見と同時に「わからなくなった」という感想も多かった。この「わからないこと」について、ダンスに関わる研究会メンバーからは「コンテンポラリーダンスを観た帰り道の感覚に似ている」という声があがる。それを聞いたモニターの一人が、見える人と見えない人について気づきがあったと言う。「ダンスってかっこいいとか楽しいものだと思っていたけど、わからないのが面白い、謎のまま持ち帰る、という体験があることを知った。見える人でもわからないんだ、見える人も遠い存在ではないんだ、と思った」。

今回、「ダンスを言葉で伝える」という試みが成立したのは、モニターである視覚障害者の積極的な「言語化」のおかげでもある。というのも、今回参加したモニターらは、わからなかったことや曖昧に感じたことも含めて、4つのディスクライブによるダンス観賞体験を率直に、丁寧に、言葉にしようとする方々だったからだ。それにより、視覚障害者にダンスやディスクライブがどのように伝わっているか、または伝わっていないのか、晴眼者だけではおよばない視点やアイデアについて議論をおこなうことができた。
また、完成品ではないダンスの習作を人前に出し、さまざまな人の視点と言葉によって揉まれることに生身で取り組んだダンサーたちや振付家の存在と、それを守ろうとしたスタッフたちによって、この研究会は成立している。アーティストや作品が脅かされることのないように、安全に議論し、模索できる場。さらにはコンテンポラリーダンスに関わる人々が「ダンスとはいったい何か」「わたしたちはダンスでなにを伝えようとしているのか」とあらためて向き合う時間ともなった。
最後に唐津さんから「コンテンポラリーダンスは、観賞の仕方に正解がないため、『わからなさ』を楽しめないと興味を持っていただくのが難しい。モニターの方々が、それを積極的に冒険として楽しんでくださっていることに感動しました。これからどういうことができるのか、ここをダンスについて共に考えていくもうひとつの出発点にしてさらに探っていきたい」という力強い言葉で、研究会は終了した。

文・河野桃子
大学にて演劇、舞台制作、アートマネジメントを学ぶ。卒業後は、海外渡航をへて帰国。週刊誌・テレビ報道・経済誌などで記者、編集者、制作者として活動。障害者の出演する舞台公演の制作などに関わりながら、現在は、演劇、コンテンポラリーダンス、舞台制作などのインタビュー・公演記事執筆、編集などをおこなう。














